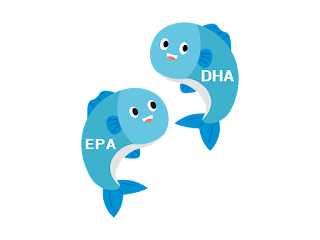検診などで脂質異常症といわれことはありませんか?脂質異常症がなくても,内臓脂肪が気になる方・糖質が大好きな方・運動不足を感じている方にも関係があるかもしれません.今回は脂質異常症について解説しながら,原因や対策について紹介していきます.
血液中にLDLコレステロールが多かったり,HDLコレステロールが少なかったり,中性脂肪が多い状態を脂質異常症と表現します.コレステロールの役割は細胞膜やホルモンの材料になるので,体に必要です.中性脂肪はエネルギーとして使われますが,多すぎると脂肪に取り込まれて体脂肪が増えます.
血液データのHDLやLDLというのはコレステロールを運ぶ役割を持っています.運ばれる「コレステロール」は共通のもので,コレステロール自体は体の材料として必要なものになります.では,HDLとLDLで何が違うのでしょうか.LDLとHDLの役割について解説していきますね.
LDLは肝臓から体の隅々にコレステロールを運ぶ役割を持ちます.一方,HDLは体の隅々から肝臓へコレステロールを回収する役割を持っています.LDLの数値が高いとコレステロールが体の隅々に届けられる量が多くなり,血管の壁に取り込まれて動脈硬化が起こるとされています.コレステロールを体の隅々に届けるのがLDLということで,LDLの数値に注意しましょうというのが血液検査から導かれる答えでした.
LDLが増える原因は食肉の油部分やバター・生クリーム・インスタントラーメンに多く含まれる飽和脂肪酸とされています.LDLを増やさない方法としては飽和脂肪酸の摂取を抑えることが重要といえます.一方で,中性脂肪増加の原因は糖質の摂りすぎにも原因があるとされています.後述するω3不飽和脂肪酸の摂取が中性脂肪の減少に効果があります.また,HDLが低い原因としては肥満や喫煙・運動不足が挙げられます.
最近の研究ではLDLの中でも,小型LDLが危険だということがわかってきました.小型LDLは『超悪玉コレステロール』とも呼ばれています.LDLよりも小型LDLの方が血管の壁に入り込みやすいということで,普通サイズのLDLはむしろコレステロールの回収という大きな役割があることが強調されています.では,小型LDLはどうやって作られるのでしょうか.実は,糖質の過剰な摂取により中性脂肪が増えて,小型LDLが増えることがわかっています.肥満や糖尿病などがあるとリスクがさらに高くなります.
LDLを小型化させるのは中性脂肪が原因ということがわかっています.インスリン抵抗性があると動脈硬化のリスクがさらに高くなります.インスリン抵抗性というのは血糖値を下げるホルモンであるインスリンが効きにくいという状態です.インスリンが血糖に作用して筋肉や肝臓に血糖を取り込みます.ですが,インスリンが効きにくいと筋肉に取り込まれにくくなってしまいます.また,筋肉や肝臓には血糖を取り込める量に限界があります.最終的に余った血糖は中性脂肪に変えられて脂肪細胞に取り込まれることで体脂肪となります.体脂肪の中でも内臓脂肪が増えてくると,次第に体がインスリン抵抗性を持つようになります.インスリン抵抗性は内臓脂肪から分泌される物質が原因で起こりますので,過剰な脂肪を蓄えないようにすることが大事です.
血糖を増やすのは糖質です.炭水化物やお菓子の食べ過ぎが糖質の過剰摂取となり,血糖値を高めます.血糖値を下げるためにインスリンが分泌されますが,内臓脂肪が多いとインスリンが効きにくくなります.その結果として,中性脂肪が多くなると小型LDLができて動脈硬化が進むということになります.そこから狭心症や心筋梗塞につながり,命に関わる病気へと進行する恐れがあります.
小型LDLを減らすにはオメガ3不飽和脂肪酸であるDHA・EPA・α–リノレン酸が有効です.魚やエゴマ油・あまに油を摂取して中性脂肪を減らすことが大事になります.内臓脂肪を減らすには糖質を減らすか,運動で血糖を消費することが有効です.最近はドラッグストアでもω3不飽和脂肪酸をアピールするPOPが貼られていますね.急いでいる場合や食生活はあまり変えたくない場合には運動がおすすめとなります.
最後になりますが,コレステロールは食べ物から摂取しなくても体内で作られます.食べ物からたくさん摂取すると,そのぶん体内で作る量を減らすようになっています.食べ物から摂取しなければ,体内で作られます.この情報からもコレステロールは体にとって必要で,ムリに制限する必要はないのがおわかりだと思います.常識の範囲内であれば,コレステロールはあまり気にせずに食べ物から摂取しても問題ありません.昔は卵を食べすぎると良くないと言われている時期もありましたが,厚生労働省のホームページからもコレステロール摂取量についての記事は明記されなくなりました.
〈まとめ〉
①脂質異常症はコレステロールと中性脂肪の数値が関与
②LDLの中でも小型LDLが危険
③小型LDLが増えるのは糖質の過剰摂取が原因
④内臓脂肪は動脈硬化の危険因子
⑤ω3(オメガ3)不飽和脂肪酸が有効
お問い合せはLINE公式アカウントhttps://lin.ee/oX4OZQiへ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
〈あなたにおすすめの記事〉
自律神経が乱れると出る症状って何?/治し方は?/整える方法は?
https://shushua2022.blogspot.com/2022/12/blog-post_53.html
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
~もみほぐしと運動で体を健康にするお店~
あなたのパーソナルトレーナーしゅしゅあ 代表TERU
〒福岡市中央区天神2丁目
ホームページ:https://shushua.net